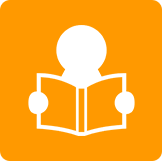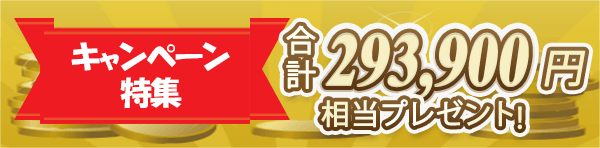- ホーム
- 株式投資関連のコラム
- 株式用語
- 巳年の相場格言「辰巳天井」の株価傾向は?干支の相場格言を紹介(2025年版)
巳年の相場格言「辰巳天井」の株価傾向は?干支の相場格言を紹介(2025年版)
2025年は「巳年(みどし)」です。株式市場には巳年にまつわる相場格言「辰巳天井(たつみてんじょう)」があります。辰巳天井とは、辰年や巳年に高値をつけるという意味です。
このコラムでは、2025年の株式市場がどうなるのか、過去の巳年のデータを見ながら考えていきます。また、干支にまつわる相場格言を騰落率とともに紹介しますので、こちらもぜひ参考にしてください。
干支の相場格言とは?
記事の冒頭でも紹介したように、巳年には「辰巳天井」という相場格言があります。辰年の前年にあたる卯年は株式市場が上昇しやすく、その流れを引き継いで辰年や巳年に高値をつけるという意味です。
干支にまつわる相場格言は、辰巳天井以外にも存在します。すべての干支に対して格言があるので、表形式で紹介します。また、直近の日経平均株価の年間騰落率も合わせて紹介するので、ぜひ見比べてみてください。
| 年 | 干支 | 相場格言 (株価傾向) |
前年終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 終値 | ||||
| 2012年 | 辰(たつ) | 辰巳天井 (好調) |
8,4553.5円 | +22.94% |
| 10,395.18円 | ||||
| 2013年 | 巳(み) | 10,395.18円 | +56.72% | |
| 16,291.31円 | ||||
| 2014年 | 午(うま) | 午尻下がり (不調) |
16,291.31円 | +7.12% |
| 17,450.77円 | ||||
| 2015年 | 未(ひつじ) | 未辛抱 (横ばい) |
17,450.77円 | +9.07% |
| 19,033.71円 | ||||
| 2016年 | 申(さる) | 申酉騒ぐ (変動 大) |
19,033.71円 | +0.42% |
| 19,114.37円 | ||||
| 2017年 | 酉(とり) | 19,114.37円 | +19.10% | |
| 22,764.94円 | ||||
| 2018年 | 戌(いぬ) | 戌笑い (好調) |
22,764.94円 | ▲12.08% |
| 20,014.77円 | ||||
| 2019年 | 亥(い) | 亥固まる (変動 小) |
20,014.77円 | +18.20% |
| 23,656.62円 | ||||
| 2020年 | 子(ね) | 子は繁盛 (好調) |
23,656.62円 | +16.01% |
| 27,444.17円 | ||||
| 2021年 | 丑(うし) | 丑つまずき (年後半に不調) |
27,444.17円 | +4.91% |
| 28,791.71円 | ||||
| 2022年 | 寅(とら) | 寅千里を走り (波乱) |
28,791.71円 | ▲9.37% |
| 26,094.50円 | ||||
| 2023年 | 卯(う) | 卯は跳ねる (好調) |
26,094.50円 | +28.24% |
| 33,464.17円 | ||||
| 2024年 | 辰(たつ) | 辰巳天井 (好調) |
33,464.17円 | +19.22% |
| 39,894.54円 |
直近のデータを見る限り、「辰巳天井」や「卯は跳ねる」、「子は繁盛」は相場格言どおりの展開となっています。「寅千里を走り」は波乱が起こりやすいことを示しており、騰落率▲9.37%である点を踏まえると、こちらも相場格言に近い状態だったと言えるでしょう。
一方で、「午尻下がり」の年は+7.12%、「戌笑い」は▲12.08%と相場格言とは逆の展開になっています。必ずしも相場格言どおりの展開になるわけではないことは、頭に入れておいたほうが良さそうです。
相場格言「辰巳天井(たつみてんじょう)」の株価傾向
続いて、辰年と巳年の年間騰落率を見ていきましょう。今回は1946年以降の辰年と巳年について、日経平均株価の騰落率を前年比で計算していきます。
辰年(たつどし)の株価傾向
辰年の株価動向を見ていきましょう。下の表は、1946年以降に7回あった辰年の日経平均株価の騰落率(前年比)をまとめたものです。7回中5回で株価が大幅上昇しており、相場格言どおりに高値をつける確率が高いと言えます。
| 年 | 前年終値 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1952年 | 166.06円 | 362.64円 | +118.38% |
| 1964年 | 1,225.10円 | 1,216.55円 | ▲0.70% |
| 1976年 | 4,358.60円 | 4,990.85円 | +14.51% |
| 1988年 | 21,564.00円 | 30,159.00円 | +39.86% |
| 2000年 | 18,934.34円 | 13,785.69円 | ▲27.19% |
| 2012年 | 8,455.35円 | 10,395.18円 | +22.94% |
| 2024年 | 33,464.17円 | 39,894.54円 | +19.22% |
日本をはじめ東洋では、辰(龍)は縁起の良い存在であり、天に向かって昇って行く姿を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。辰巳天井という相場格言は、とてもぴったりですね。
なお、1964年に株価が下落した理由は、1958年6月から1961年12月まで続いた「岩戸景気(いわとけいき)」の反動や、四大証券会社の一翼を担っていた山一證券の経営悪化が原因と考えられます。
2000年の株価下落理由は、1999年から2000年にかけて通信・IT関連企業の株価が急騰した「ドットコムバブル(ITバブル)」の崩壊が関係しているようです。
巳年(みどし)の株価傾向
続いて、巳年の株価動向を見ていきましょう。辰年と同じように、1946年以降に6回あった巳年の日経平均株価の騰落率(前年比)を表にまとめました。巳年も6回中4回で株価が上昇しているのがわかりますね。相場格言どおり、高値をつける確率が高いと言えるでしょう。
| 年 | 前年終値 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1953年 | 362.64円 | 377.95円 | +4.22% |
| 1965年 | 1,216.55円 | 1,417.83円 | +16.55% |
| 1977年 | 4,990.85円 | 4,865.60円 | ▲2.51% |
| 1989年 | 30,159.00円 | 38,915.87円 | +29.04% |
| 2001年 | 13,785.69円 | 10,542.62円 | ▲23.52% |
| 2013年 | 10,395.18円 | 16,291.31円 | +56.72% |
1977年に株価が下落した理由として、明確なものは見つかりませんでした。前年の1976年には株式市場が高値をつけているので、その反動と考えられます。2001年には20%を超える下落となっていますが、こちらは2000年と同じでドットコムバブルの崩壊が関係しているようです。
巳年の2025年の株価はどうなる?
巳年である2025年も、相場格言どおり「辰巳天井」になるかもしれません。今年はプラス要素とマイナス要素が入り混じる展開となりそうです。具体的にどのような材料があるのか表に整理しました。
| 材料 | 株式市場への影響 |
|---|---|
| ①アメリカの金融緩和 | ・2025年の政策金利引き下げ見通しは2回だが、オフィスなどの商業用不動産ローンを巡る危機や景気後退が発生する可能性が高く、FRBによる緊急的な金融緩和によって株高になる ・インフレが再燃し、インフレに強い資産として株式が好まれる |
| ②日本の金融緩和的な環境 | 日銀が政策金利をゆっくりと引き上げる可能性が高いが、インフレ率と比べて現状の政策金利が大幅に低く、金融緩和的な環境が継続する |
特に「商業用不動産ローン(CREローン)を巡る危機」には要注意です。アメリカにある中小銀行の貸出金額の約半分が商業用不動産ローンで構成されているのですが、そのローンが債務不履行(デフォルト)に陥るリスクが高まっています。
理由は、オフィス価格が下落しているからです。アメリカではコロナ化をきっかけにテレワークが浸透し、オフィス需要が縮小しました。オフィス自体の資産価格下落に加えて賃料収入も減少しており、オーナーの資金繰りが悪化しているのです。
現在はローンの契約期間延長や金利減免で耐えていますが、耐えきれずに商業用不動産ローンが債務不履行に陥った場合、銀行危機に発展するおそれがあります。ただし、危機が起きた場合にはFRBが緊急的な利下げを実施するでしょう。利下げは株式市場にプラスなので、再び株価は上昇に転じると考えられます。
最終的には2025年末にかけて株価が上昇していき「辰巳天井」となる可能性があります。しかし、株式市場を取り巻く環境は常に変化しており、さまざまな要因が複雑に絡み合って動いています。経験則を信じすぎず、あくまで参考程度に見ておくのがおすすめです。
まとめ
過去のデータから、辰年や巳年は株式市場が大きく上昇する可能性が高いことがわかりました。巳年である2025年は、不安要素がありつつも、最終的には相場格言どおりに株価が上昇するかもしれません。
相場格言は、長期にわたって蓄積された株式市場の経験則に基づいたものです。参考になるものも多くありますが、株式市場は常に多くの要因が複雑に絡み合って動いています。これらの格言が常に当てはまるわけではない点に注意してください。
この記事を見た人は、こちらも読んでいます