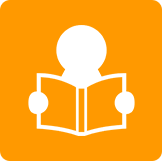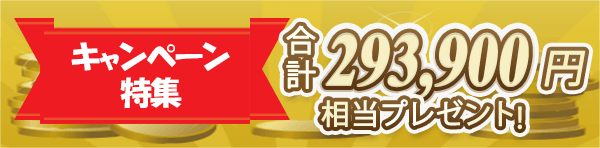- ホーム
- 米国株投資のはじめ方(目次)
- 米国株(アメリカ株)の今後(2025年4月)の見通しと3月の振り返り
米国株(アメリカ株)の今後(2025年4月)の見通しと3月の振り返り
- お知らせ
- 2025年5月の最新の米国株(アメリカ株)の見通しは、こちらで解説しています!
米国株市場の2025年3月の振り返りと、2025年4月の見通し、注目イベント、投資戦略についてご紹介します。
本記事のポイントは、次の3つです。
ポイント
- 3月は主要3指数揃って値下がり
- 4月は値動きの荒い展開に
- 月半ばから2025年第1四半期の企業決算がスタート
詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
2025年3月の米国株市場を振り返り
3月の米国株式市場はダウ工業株30種平均とS&P500、ナスダック総合株価指数の主要3指数が揃って値下がりしました。月間ベースでは、ダウ平均が前月比4.2%安、S&P500は同5.8%安、ナスダック総合は8.2%安になります。
<3月は主要3指数揃って値下がり(年初来)>
出典:TradingView
S&P500セクター別の月間騰落率をみると、唯一「エネルギー」が値上がりしました。一方、「コミュニケーションサービス」や「一般消費財」などは大きく売り込まれています。
S&P500は3月13日、最高値をつけた2月19日からの値下がり率が10.1%となり、「調整局面」入りとされる10%を超えました。
米調査会社ヤルデニ・リサーチによると、S&P500は1928年以降、調整局面は56回ありました。そのうち22回は直近高値から20%以上の値下がり率となる弱気相場に陥っています。
| 分類 | 1928年以降発生した回数 | 高値から安値までの 値下がり率(平均) |
期間(平均) |
|---|---|---|---|
| 調整局面 | 36回 | 13.8% | 115日 |
| 弱気相場 | 22回 | 35.6% | 341日 |
※1 参考:Stock Market Historical Tables: Bull & Bear Markets(ヤルデニ・リサーチ)
調整局面全体で高値から安値までの値下がり率は13.8%、平均で115日間続いています。ただし、弱気相場入りしてしまうと、高値から安値までの値下がり率は平均で35.6%に達し、341日続いており、市場の動向を注視する必要があるでしょう。
第2次トランプ政権(トランプ2.0)による関税政策を巡る不確実性の高まりを背景に、2月に引き続きリスク回避姿勢が強まりました。株式市場で多くの弱気サインが点灯するなか、家計や企業の心理を映す「ソフトデータ」の悪化が目立っている状況です。
例えば、14日に発表された3月米ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)は57.0と、前月の64.7から低下しました。消費者の5年先の予想インフレ率は4.1%と、1993年2月以来となる32年ぶりの高水準となりました。
<期待指数は高所得者層の減少幅が最も大きい>
出典:ミシガン大学
物価高と景気悪化が同時に進む「スタグフレーション」や、トランプ氏と景気後退(リセッション)をあわせた造語「トランプセッション(トランプ不況)」の警戒感が高まっていることがうかがえます。
なお、他の調査でも似た結果が出ていますが、同調査が実際の状況より党派的なバイアスがかかっているのかもしれないことに留意してください。
19日に開催したFOMC(米連邦公開市場委員会)では、米連邦準備理事会(FRB)が政策金利の据え置きを決定しました。政策金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標は4.25〜4.5%で維持されます。
<2回連続で据え置かれたFF金利(%)>
出典:セントルイス連銀
パウエルFRB議長は7日、労働市場は堅調であり、追加利下げを「急ぐ必要はない」との見解を示しました。さらに、FOMC後の記者会見では、トランプ2.0の各種政策を踏まえて「見通しの不確実性は異常なほど高まっている」と強調しています。
さらに、FRBが重視する米個人消費支出(PCE)物価指数は、食品とエネルギーを除くコア指数が市場予想を上回る伸びとなりました。
パウエル議長の発言に加え、トランプ政権の政策の影響でインフレ懸念が燻るなか、少なくとも早期において、積極的な金融緩和が景気や株価を支える「FRBプット」への期待は薄れてきているといえます。
市場で注目されていたFOMC参加者による経済見通しでは、2025年中の利下げ回数を2回と想定し、前回昨年12月の見通しを維持しました。
| 項目 | 前回(2024年12月予想) | 今回 |
|---|---|---|
| 政策金利 | 3.9% | 3.9% |
| PCE物価指数 | 2.5% | 2.7% |
| GDP成長率 | 2.1% | 1.7% |
| 失業率 | 4.3% | 4.4% |
※5 参考:Press Release(FRB)
実質国内総生産(GDP)成長率は1.7%と中長期の巡航速度とされる1.8%と同程度に減速する一方、個人消費支出(PCE)物価指数は2.5%から2.7%に引き上げられました。政策の不確実性が高まるなか、今後もデータを注視する必要がありそうです。
市場では6月までに利下げを再開するとの予想が有力です。米金利先物の値動きから金融政策を予想する「CME FedWatchツール」によると、3月30日時点において6月のFOMCで政策金利を0.25%以上の引き下げを見込む確率は8割強となります。
<FedWatch(2025年6月)>
出典:CME Group
2025年4月の見通し
4月の米国株式市場は、トランプ関税による米景気への先行き不透明感が強まるなか、値動きの荒い展開になると想定します。
トランプ大統領は2日、世界各国からの輸入品に対して「相互関税」をかけると公表しました。市場の想定以上にきびしい内容であり、世界的に報復関税の応酬がなされれば、米国を含む世界経済に大きな影響を及ぼす見込みです。今後、相互関税の発動によるインフレ圧力や生産などへのネガティブな影響を見極める段階に入るため、株式市場は不安定な値動きが続くでしょう。
関税免除・引き下げに向けた米と各国との交渉がおこなわれる場合は、トランプ氏による日々の発信内容によって市場は一喜一憂する展開となりそうです。
米株式市場の2日の取引時間外の動きをみると、ダウ平均の先物が一時1,000ドル超値下がりしたほか、M7や自動車なども大幅安になるなど、リスク回避の動きが強まっている状況です。
マクロ面では、米アトランタ連銀が4月1日に更新した経済指標から国内総生産(GDP)を予測する「GDPナウ」は、2025年第1四半期の成長率がマイナス3.7%と、前回公表時(3月28日)のマイナス2.8%から一段と落ち込みました。
4月1日発表の3月の米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景況感指数などが悪化したことが、GDPナウの一段の落ち込みにつながっています。足元ではソフトデータの悪化が目立ちますが、実体経済にも影響が及んでいくかどうかを確認する上でハードデータにも注目する必要があるでしょう。
月半ば以降は投資家の目線が再び企業業績に向かう見込みです。4月11日よりJPモルガン・チェース(JPM)をはじめとする米主要企業の決算発表がはじまります。
ファクトセットが集計したアナリスト予想によると、S&P500構成銘柄の2025年第1四半期の予想1株あたり利益(EPS)は前年同期比7.3%増と、2024年末時点の11.7%から急減速しました。
2025年第2四半期には9.3%増、第3四半期には11.9%増、第4四半期には11.4%増と、年後半は2桁の成長率へと高まる見通しですが、トランプ関税などの影響を受けて企業業績の下振れリスクが懸念されます。
S&P500構成銘柄の予想株価収益率(PER、12か月フォワード)は20.5倍と、過去5年の平均である19.9倍、過去10年平均の18.3倍と比較して依然として割高な水準となります。
注目イベント、投資戦略
二転三転するトランプ2.0の政策を予想することはむずかしいですが、投資判断の根拠は企業業績などのファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に回帰します。
また、トランプ2.0下において、今後は減税や規制緩和など成長を後押しするための政策に軸足をシフトしていく可能性があります。ウォール街のストラテジストは2025年末にかけてS&P500が値上がりするシナリオを堅持してもいます。
S&P500は過去15年間に9回の調整局面(うち2回は本格的な弱気相場)入りしました(出所:モトリーフール)。9回の調整局面のうち8回、つまり約9割は翌12か月間でプラスのリターンを達成しており、平均18%の値上がりを記録しています。
これらのことを踏まえると、トランプ関税に絡む不透明な時期が長引く公算が高いなか、好業績銘柄の押し目を拾うにしても、徐々に買い増しするスタンスが有効となりそうです。関税の影響を受けづらく、ディフェンシブ性の高い銘柄は引き続き底堅い値動きとなるでしょう。
経済イベントとしては、4日に雇用統計の発表後にパウエル議長の講演を控えています。早期の金融緩和を期待するのはむずかしい状況ですが、インフレ動向やトランプ関税の影響などに関する見解に注目です。
その他、3日のISM非製造業景況感指数、4日の雇用統計、9日にFOMC議事要旨、10日に米消費者物価指数(CPI)、16日に小売売上高、30日の1~3月期GDP速報値、PCEデフレーターなどの発表を控えています。
| 日付 | 指標名 | 補足 |
|---|---|---|
| 4月3日 | ISM非製造業景況感指数 | サービス業の景況感 |
| 4月4日 | 雇用統計 | 失業率・非農業部門雇用者数など |
| 4月9日 | FOMC議事要旨 | 前回会合の内容を確認 |
| 4月10日 | 米消費者物価指数(CPI) | インフレの注目指標 |
| 4月16日 | 小売売上高 | 個人消費の動向 |
| 4月30日 | 1~3月期GDP速報値、PCEデフレーター | 成長率と物価動向の指標 |
moomoo証券は米国株初心者におすすめ!
moomoo証券は、米国株投資をこれからはじめようと考えている投資初心者の方におすすめの証券会社です。
注目ポイントはこの3つ
- 取引手数料が業界最安水準
- 1ドルから米国株に投資可能
- 情報満載のアプリが無料で使える
取引手数料を比較してみましょう。
| 証券会社 | 取引コスト | ネット証券 詳細情報へ |
|
|---|---|---|---|
| 売買手数料 (税込) |
為替手数料 (1ドルあたり) |
||
| moomoo証券 (ベーシックコース) |
0.132% (最低0米ドル※1) |
無料 | |
| moomoo証券 (アドバンスコース) |
一律2.18米ドル (200株まで) |
無料 | |
| 松井証券 | 0.495% (最低0米ドル※2) |
無料 | |
| SBI証券 | 0.495% (最低0米ドル※1) |
0銭または25銭※3 | |
| 楽天証券 | 0.495% (最低0米ドル※1) |
0銭または25銭※3 | |
| マネックス証券 | 0.495% (最低0米ドル※1) |
0銭または25銭※4 | |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧 auカブコム証券) |
0.495% (最低0米ドル※2) |
20銭 | |
(2026年1月現在)
※1 ベーシックコースの取引手数料は、約定代金が8.3米ドル以下なら0円、166,66.666米ドル以上なら22米ドルが上限です。
※2 約定代金が2.22米ドル以下の取引なら、売買手数料は0米ドル(無料)になります。
※3 リアルタイム為替取引の場合、0銭/ドルになります。
※4 日本円→米ドルへの為替手数料は0銭/ドル、米ドルから日本円への為替振替時は25銭/ドルとなります。
このように、2つの手数料コースは主要ネット証券と比較して、どちらもかなり安く設定されています。
また、moomoo証券では、米国株の端株(はかぶ)取引サービス「micro米国株」を提供しています。米国株は1株単位での取引が基本ですが、micro米国株を使うと1株未満、1ドルから米国株に投資可能です!
さらに、moomoo証券に口座開設した方限定で「moomooプレミアム」が無料で使えるようになります。
moomooプレミアムで使える機能(一例)
- 大口投資家の売買動向
- 会社四季報
- リアルタイム株価
- 著名投資家レポート
- 日経CNBC動画
有料級の情報を無料で入手できるのは、moomoo証券に口座開設した人だけの特権です。まだmoomoo証券の口座を持っていない方は、いますぐ口座開設しましょう。
当サイト経由でmoomoo証券に口座開設すると、最大100,000円相当の株の買付代金と、当サイト限定のタイアップレポート「moomooアプリ完全攻略レポート」をプレゼントさせていただくキャンペーンを実施中です!
まとめ
2025年3月の米国株市場は、主要3指数が揃って下落し、S&P500は調整局面に入りました。背景には、第2次トランプ政権による関税政策への懸念や、景気・物価双方への不安があり、市場にはリスク回避の姿勢が強まりました。
4月については、相互関税の発動リスクや企業業績の見通しに左右される相場展開が想定されます。特にトランプ政権の発言・政策によって、マーケットのボラティリティが高まる場面も増えそうです。
ただし、過去の調整局面ではその多くが1年以内に回復していることを踏まえれば、悲観一辺倒ではなく、好業績銘柄の押し目を見極めつつ、中長期目線での投資戦略が有効と考えられます。
今後の米国市場は、トランプ政策やインフレ動向、金融政策の変化、企業決算などさまざまな要因が交錯する展開が続きます。最新の経済データや政策の動向を注視しながら、柔軟に対応していくことが重要です。