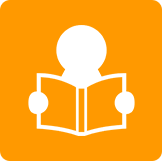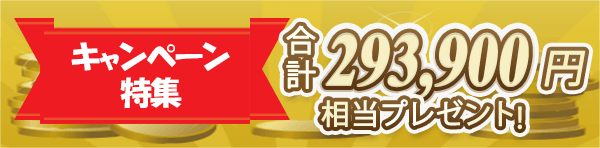- ホーム
- 株式投資関連のコラム
- 株式用語
- 投資初心者は何から始める?株初心者に向けた株式投資の始め方・勉強方法を解説
投資初心者は何から始める?株初心者に向けた株式投資の始め方・勉強方法を解説
テレビや雑誌、友人との会話の中で投資に興味を持つ人が増えています。しかし、「何からはじめればよいかわからない」というのが共通の悩みではないでしょうか。結論としては、「証券会社への口座開設と入金」から取り組めばOKです。
この記事では、投資初心者が株式投資をはじめるまでにやるべきことや勉強方法などについて、6つのステップに分けてわかりやすい言葉でていねいに解説します。ぜひ最後まで読んでいただき、一緒に投資をはじめましょう!
ステップ① 投資を始める準備
最初のステップとして、証券会社への口座開設と入金をしましょう。口座開設はWebで完結します。スマートフォンやパソコンを使って必要事項を入力し、本人確認書類を提出するだけで、最短翌日に完了します。
このように口座開設自体はとてもかんたんなのですが、“証券会社選び”というハードルが存在します。世の中に証券会社が1社しか存在しなければとても楽なのですが、現実ではたくさんの証券会社が存在します。このため「どの証券会社にすればよいかわからない」という課題に、投資初心者は必ず直面するのです。
このセクションでは、証券会社の種類と選び方、おすすめの証券会社を紹介します。また、一緒に口座開設しておきたい「NISA(ニーサ)口座」や入金についても説明しますね。
① 証券口座の開設
証券会社には、大きく分けて「総合証券」と「ネット証券」の2種類があります。総合証券は対面式で証券マンが対応してくれる証券会社、ネット証券はネット上で取引が完結する証券会社です。
このうち、投資をはじめる方におすすめしたいのは「ネット証券」となります。大手のネット証券であれば取引手数料が無料のところが多く、口座管理料も発生しません。ネット証券の取引手数料が無料なのは、証券の取引を機械化して人件費を減らしているからです。
なお、証券会社の手数料体系を調べると、「1注文ごとの取引額」と「1日の合計取引額」の2つのパターンが用意されています。手数料が有料だった時代は、ご自身の取引スタイルに合わせて選ぶ必要がありました。
2025年3月現在、SBI証券や楽天証券、moomoo証券であれば手数料が一律無料なので、取引額を気にする必要はありません。あとは3社のうちから証券会社を選べばOKです。各社が口座開設キャンペーンを実施しているので、キャンペーンが気になった証券会社に口座開設してみましょう。
| 証券会社名 | 手数料 | おトク情報 + ネット証券詳細情報へ |
|---|---|---|
| SBI証券 | 一律無料 | 限定タイアップ
現金2,500円+オリジナルレポートがもらえる |
| 楽天証券 | 現金1,000円がもらえる |
|
| moomoo証券 | 限定タイアップ
最大10万円+オリジナルレポートがもらえる |
このほかにも、ネット証券はたくさんあります。各社がさまざまな便利ツール&キャンペーンを展開しているので、ぜひチェックしてくださいね。詳しくは下記のページをご覧ください。
関連記事
NISA口座の開設
証券会社に口座開設する際、「NISA(ニーサ)口座の開設」を申し込む画面が出てきます。はじめて証券口座を開設する方は、一緒にNISA口座を開設しておくとよいでしょう。
NISAとは、「株や投資信託(投信)などの運用益や配当を、一定額非課税にする制度」のことです。通常は投資で得た利益に対して20.315%の税金が掛かります。100万円の利益が発生した場合、約20万円を税金として納めることになるため、手元に残る利益は約80万円に減る計算です。
NISA口座の場合、100万円の利益が発生したとしても税金は掛からないので、利益の100万円がそのまま手元に残ります。本来なら税金として納めていたはずの20万円を投資に回せるので、投資家にとって非常にありがたい制度です。効率よく資産を増やすためにも、NISA口座を活用したいですね。
ただし、NISAには注意点が2つあります。
NISAの注意点
- NISA口座は1人1つしか開設できない
- 損益通算ができない
注意点1つ目は「NISA口座は1人1つしか開設できない」点です。通常の証券口座とは違って複数のNISA口座を持つことはできないので、注意してください。
国内株投資をするなら、ネット証券の多くが売買手数料を完全無料にしているので、どこでNISA口座を開設しても差はありません。先ほど「①証券口座の開設」でおすすめしたSBI証券や楽天証券、moomoo証券の中から選ぶとよいでしょう。
注意点2つ目は「損益通算ができない」点です。損益通算とは、株式投資で損失が出た場合に、他の利益と合わせて税金額を減らせる制度となります。NISA口座では、利益が非課税になる代わりに損失が出ても損益通算ができません。とはいえ、非課税によるメリットのほうが大きいので、NISAを積極活用したいですね。
NISAについて調べていると「新NISA」という表記も出てきます。これは2024年1月からはじまったNISAの新制度です。従来のNISAで定められていた非課税期間が無期限となり、年間投資枠が拡大されました。投資家にとって、うれしいアップデートですね。
NISAについてかんたんに説明してきました。この制度を活用すると、税金の支払いがない分、効率的に資産形成できます。少額で投資をはじめる場合は特に、NISA口座を開設するとよいでしょう。
② 証券口座への入金
証券会社への口座開設が終わったら、証券口座に投資資金を入金しましょう。入金手続きはとてもかんたんです。証券口座にログインした後、画面の指示にしたがって入金手続きを進めればOKとなります。
証券会社ごとの入金方法は、当サイトの下記ページで詳しく解説しています。こちらを参考に入金してみてくださいね。
| 証券会社名 | 入金手続き解説ページ |
|---|---|
| SBI証券 | |
| 楽天証券 | |
| moomoo証券 |
ステップ② 投資する商品を選ぶ
投資をはじめる準備が整ったら、投資する商品を選びましょう。世の中にはさまざまな金融商品が存在しており、具体例を挙げると預金や株式、投資信託、ETF、金、債券、不動産などがあります。かんたんに、各金融商品の特徴を説明しますね。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 預金 | 銀行や信用金庫などの金融機関に資金を預け入れるもの。普通預金、定期預金などがある。元本保証があり安全性が高いが、低金利環境では利回りは低い。預金保険制度により一定額まで保護される。 |
| 保険 | 生命保険や医療保険など、リスク対策として加入する金融商品。万一の事態に備える保障機能が主だが、貯蓄性の高い保険商品も存在する。 |
| 株式 | 企業の所有権の一部を表す有価証券。株主は企業の利益の一部を配当として受け取る権利や、株主総会での議決権を持つ。株価の値上がりによるキャピタルゲインも期待できるが、企業業績や市場環境により価格変動リスクがある。 |
| 投資信託 | 投資家から集めた資金をプロの運用者(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資する商品。少額から多様な資産に投資できる利点があるが、運用成績により元本割れのリスクがある。信託報酬などの手数料がかかる。 |
| ETF | 上場投資信託(Exchange Traded Fund)の略。株式と同様に取引所で売買できる投資信託。特定の指数(日経平均やTOPIXなど)に連動するよう設計されており、分散投資と流動性を兼ね備える。投資信託より低コストで取引可能だが、市場価格の変動リスクがある。 |
| 金 | 貴金属の一種で、インフレヘッジや有事の際の資産保全手段として利用される。現物の金地金や金貨のほか、金ETFや金鉱株などの形で投資可能。長期的な価値保存手段となりうるが、現物保有の場合は保管コストや純度の問題がある。 |
| 債券 | 政府や企業が資金調達のために発行する借用証書。一定期間ごとに利子(クーポン)が支払われ、満期時に元本が償還される。国債は安全性が高く、社債は発行体のリスクに応じて金利が高くなる傾向がある。金利変動や発行体の信用リスクがある。 |
| 不動産 | 土地や建物などの実物資産。賃貸収入(インカムゲイン)と値上がり益(キャピタルゲイン)が期待できる。インフレヘッジにもなりうるが、流動性が低く、維持管理コストや税金がかかる。立地や物件の状態、経済環境により価格変動リスクがある。不動産投資信託(REIT)を通じた間接投資も可能。 |
今回は大まかな金融商品の種類のみを紹介しましたが、預金であれば「普通預金」と「定期預金」がありますし、株式であれば「日本株」や「米国株」、「成長株」や「高配当株」といった区分に分けることも可能です。当サイトは「日本株への投資」がメインなので、この後は日本株を例に説明します。
関連記事
ステップ③ 投資の勉強をする
投資する金融商品の大枠を決めたら、その中から投資する商品を選びます。日本株への投資の場合、上場する約4,000社の企業から自分の目利きで投資先を選ばなくてはなりません。
この際、投資や銘柄選定の知識を持たずに選んでしまうと、知らず知らずのうちに倒産リスクの高い銘柄に投資していた、ということもあるでしょう。自分の大切な資産を守るためにも、投資の知識を身に着ける必要があります。
日本株へ投資する場合、おすすめの勉強法は下の3つです。
おすすめ勉強法3選
それぞれ説明しますね。
① 株初心者入門講座を読む
1つ目の勉強法は、当サイトの「株初心者入門講座」を読むことです。この講座では、株式投資の基礎や管理人ひっきーの投資に対する考え方、投資手法などを無料で公開しています。
<株初心者入門講座>

講座は「株式投資の基本」と「株式投資の応用」の2項目に分かれており、投資スタイルの決め方や株式市場の基礎知識、財務諸表や株価チャートの読み方まで、投資に必要な正しい知識をわかりやすく解説しています。
株式投資に挑戦するには、少し専門的な知識を学ばなければなりません。投資本を開いたときに「むずかしそう」と感じて読むのをやめてしまった経験がある方もいらっしゃるでしょう。
当サイトでは、中学生でも理解できるように、ていねいでわかりやすい説明を心がけています。さらに、株初心者入門講座は1回あたりの分量も少なく、サクサク読み進められる設計です。ぜひ最後まで読んでいただき、株式投資に必要な正しい知識を身に着けていきましょう。
関連記事
② おすすめの投資本を読む
株初心者入門講座で株式投資に必要な知識を一通り学んだら、本を読んで理解を深めましょう。
当サイトおすすめの投資本には、エナフンさんこと奥山月仁さんの『世界一やさしい株の本』と『エナフン流株式投資術』、当サイト管理人のひっきーが書いた『はじめての株1年生』と『本当に儲かる株・成長する株を自分で見つけられるようになる本』があります。
本のおすすめ理由について、下記のページで詳しく解説中です。ぜひ参考にしてくださいね。
関連記事
③ 株オフ会に参加する
株オフ会に参加することも、投資の勉強においてとても有意義です。日本全国で株オフ会や投資イベントが毎週のように開催されており、会場開催だけでなくオンライン開催もあります。特にオンライン開催は気軽に参加できるので、株オフ会に参加した経験のない方におすすめです。
多くの株オフ会は、信頼できる有名な個人投資家さんが運営されています。しかし、はじめて参加する場合は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。そこで、当サイトの管理人や編集部が参加した株オフ会や投資イベントの中で、初心者の方に自信を持っておすすめできるものを紹介します。
当サイトおすすめの株オフ会は、yamaさんが主催されている『Kabu Berry』、エースさんが主催されている『KabuLink』です。それぞれどのような内容の株オフ会なのか、表に整理しました。
| Kabu Berry | KabuLink | |
|---|---|---|
| 概要 | 株好きなら誰でも参加OKの、個人投資家交流会&個人投資家講演会 | 参加者が銘柄を持ち寄ってプレゼンし、分析結果や気になる点をディスカッションする会。 |
| 主催者 | yamaさん | エースさん |
| 直近イベント | Kabu Berry 12月27日(土)13:00~18:00 【終了 次回未定】 参加費:無料※1 |
KabuLink93 1月24日(土)13:00~17:00 参加費:1,500円※2 |
| おすすめ ポイント |
・充実の投資家交流会 ・投資のヒントが得られます ・信頼の運営実績 |
・他の投資家さんの分析手法や着眼点が学べる ・自分自身がプレゼンすることで、分析レベルを各段に向上させることも可能 |
※1 オンラインは無料です。会場参加は1,500円です。
※2 プレゼンされる方は1,000円です。
やさ株編集部おすすめのコースは、下のとおりです。
やさ株編集部おすすめの株オフ会参加コース
- Kabu Berryにオンラインで参加する
- Kabu Berryの会場に足を運び投資家さんと交流する
- KabuLinkに参加して他の投資家さんの分析を学ぶ
- KabuLinkに参加して自分の分析をプレゼンする
この4つのステップを踏むことで、投資家としてのレベルを各段に引き上げることができます。②からスタートしてもよいのですが、株オフ会にハードルを感じる方は、①のオンライン参加からはじめてみましょう。
Kabu Berryではたくさんのオンラインセミナーが開催されていますが、おすすめは週末に「会場+オンライン」で開催されている会です。企業のIR担当者のセミナーと質疑応答があり、質疑応答では投資家さんとIR担当者との生のやり取りを見ることができます。株オフ会の雰囲気を掴めるのでおすすめです。
株オフ会の雰囲気を掴んだら、実際に会場に足を運んでみましょう。オンラインとは違った臨場感を味わえますし、他の投資家さんと交流することで、さまざまな学びが得られます。
慣れてきたら自分の保有株や気になっている銘柄のプレゼンにも挑戦しましょう。「自分の分析はレベルが低くて発表できない」と思ってしまうものですが、温かく聞いてくれる方ばかりですし、間違っていても何も恥ずかしいことではないので、勇気を出してプレゼンしてみましょう。
質疑応答では、話を聞いてくれた投資家さんからの質問を通して、自分が気付かなかった点や新たな視点を得られます。プレゼンが終わったあとは、自分の成長が実感できるはずです。
株オフ会は、ここで紹介したもの以外にもたくさん開催されています。下のページに詳細をまとめているので、株オフ会探しの参考にしてくださいね。
関連記事
ステップ④ 投資手法を決める
株式投資の基本的な知識を手に入れたら、自分自身が挑戦する投資手法を決めましょう。投資手法とは、武道や茶道でいうところの「流派」のようなものです。自分の興味が持てる投資手法に挑戦するのがよいですが、世の中には投資の流派がたくさん存在するので、初心者が選ぶのは大変でしょう。
そこで、たくさんの投資手法の中から、やさ株編集部おすすめの投資手法をピックアップして紹介します。
投資手法は何がある?
世の中にはたくさんの投資手法が存在しますが、今回はその中から代表的な7つの投資手法を紹介しましょう。
| 投資手法 (★はおすすめ度) |
投資手法の説明 |
|---|---|
| ①成長株投資法 ★★★★ |
企業の将来性を吟味して、株価の上昇余地を考え、成長性を期待する投資法。別名「グロース株投資」。 |
| ②割安株投資法 ★★★★ |
株価や資産などから評価して、資産から見た割安株を発掘し、値上がりを待つ投資法。別名「バリュー株投資」。 |
| ③IPO株投資法 ★★★ |
IPOのブックビルディングに申し込みをして、初値の値上がり益を狙う投資法。 |
| ④高配当株投資法 ★★ |
高配当銘柄に注目して、値上がり益、配当をおいしくいただく投資法。 |
| ⑤優待株投資法 ★★ |
優待銘柄に注目して、値上がり益、株主優待をおいしくいただく投資法。 |
| ⑥パニック株投資法 ★★ |
企業の不祥事などの後に起きる“パニック売り”を狙い、リバウンドを期待する投資法。 |
| ⑦モメンタム投資法 ★ |
株価の推移から判断し、右肩上がりを続けている会社を狙う投資法。 |
株初心者の方は、上に挙げた7つの投資手法の中から興味のある投資手法を選ぶのがおすすめです。迷った場合は、王道の投資手法である「成長株投資法」、もしくは「割安株投資法」に挑戦してはいかがでしょうか。
“一度投資手法を決めたら変えてはいけない”といった決まりはないので、最初に選んだ投資手法を実践する途中で他の投資手法に興味が出てきたら、そちらの手法を試してみるのもよいでしょう。
「成長株投資法をメインとしつつ、欲しい株主優待を手に入れるために優待株投資法を組み合わせる」のように、複数の投資手法を組み合わせる手もあります。表の投資手法名には、詳しく説明したページへのリンクを設置しているので、そちらもセットでご覧ください。
著名投資家の手法を参考にしよう
自分にとって興味が持てる投資手法を見つける方法のひとつとして、著名投資家の投資手法を参考にするのもおすすめです。
当サイトでは、資産バリュー投資家として有名な「かぶ1000さん」やバリュー投資家の「名古屋の長期投資家さん(なごちょうさん)」をはじめ、多くの著名投資家インタビューをたくさん載せています。
投資手法を探す際の参考になるだけでなく、投資家としてのモチベーションを高めてくれる内容となっているので、株初心者の方はぜひ読んでくださいね。インタビュー記事は、下のページにまとめています。
関連記事
ステップ⑤ 銘柄選定をする
投資手法が決まったら、投資する銘柄を選んでいきましょう。ここでは、下の3つの方法を紹介します。
銘柄選定における3つの方法
それぞれ見ていきましょう。
① スクリーニングを使う
1つ目は、銘柄選定の基本である「スクリーニングツール」を使う方法を紹介します。このツールは、自分が投資する銘柄に求める条件を指定して検索し、一瞬で投資先候補を洗い出せる点が便利です。
スクリーニングツールは、各証券会社が用意しているので、口座開設するだけで誰でも無料で使えます。購入する必要はないので、安心してくださいね。
例として、SBI証券のスクリーニングツールを紹介します。下の画像をご覧ください。PERや配当利回り、営業利益率、自己資本比率など、投資先を見極めるための指標が並んでいますね。
割安な銘柄を洗い出したい場合は「PER15倍以下」、財務健全性が高い銘柄を洗い出したければ「自己資本比率30%以上」のように条件を指定しましょう。条件を指定して検索すると、自分が理想とする条件に見合った銘柄が一瞬で表示される仕組みです。
スクリーニングツールがなかったときは、会社四季報をめくりながら条件に合う銘柄を探す必要がありました。スクリーニングツールを使えば、このような手間はかからず一瞬で銘柄を見つけられるので、積極的に活用していきたいですね。
スクリーニングツールでは、先ほど挙げた条件以外にも、さまざまな条件を指定できます。また、数値をどのように設定すべきかも迷うポイントです。そこで、やさ株編集部では成長性のある銘柄を割安な価格で投資できるよう、下のスクリーニング条件をおすすめしています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①規模:小型株(時価総額501位以下) | 事業規模 |
| ②PER:15倍以下 | 収益から見た割安性 |
| ③ROE:10%以上 | 資金の効率性 |
| ④自己資本比率:30%以上 | 財務健全性 |
| ⑤過去3年平均売上高成長率:10%以上 | 成長性 |
| ⑥売上高営業利益率:10%以上 | 収益性 |
各スクリーニング条件の詳しい説明は、下の記事にまとめています。こちらもセットでご覧ください。
② 投資関連のイベントや株オフ会に参加する
2つ目は、投資関連のイベントや株オフ会に参加する方法です。株オフ会については、ステップ③の「株オフ会に参加する」で説明したので省略します。
投資関連のイベントは、世の中でたくさん開催されています。株式投資だけでなく、FXをはじめ他の投資を含めたイベントもあり、参加してみると視野が広がってとてもおもしろいです。
しかし、初心者の方にとっては投資関連イベントを選ぶのも大変ですよね。今回は、やさ株編集部が実際に足を運んでみて、自信を持っておすすめできるイベントを2つ紹介します。
| イベント名 (開催場所) |
日程 | 概要 |
|---|---|---|
| 日経・東証IRフェア (東京) |
2026年8月28日~ 8月29日 |
日本経済新聞社と日本取引所グループの共催で開催されるイベント。企業がブース出展しており、IR担当者から直接話を聞いたり質問したりできる。著名投資家のセミナーも開催されている。 |
| 名証IR EXPO (名古屋) |
2026年12月4日~ 12月5日 |
名古屋証券取引所が主催のイベント。名証に上場している企業がブース出展しており、IR担当者と直接コミュニケーションが取れる。近年はKabu Berryプレゼンツのセミナーも目玉のひとつ。 |
今回取り上げた2つのイベントは、どちらも企業がブースを出展しています。このようなイベントには、個人投資家の認知度を高めたいと考えている企業が多く集まっているので、日常生活ではあまり触れることのない企業の情報を集められます。
例えば、工業製品や部品を作っている企業は、自社製品が展示されていることも多く、大人の社会科見学のような楽しみ方もできるでしょう。実際にIR担当者の方とお話してみると、決算書では見えてこない強みや魅力が見つかることも多いです。視野が広がるので、ぜひ足を運んでみましょう。
③ ニュースをチェックする
3つ目は、ニュースのチェックです。企業の業績は世の中の動きに影響を受けるので、「世の中で何が起きているのか」を把握しておきたいものです。また、ニュースで取り上げられた流行の店や商品が投資先の発掘に役立つ場合もあります。情報の宝庫なので、チェックする習慣を付けましょう。
ニュースは、テレビや新聞、Webサイト、アプリなどさまざまな媒体からチェックできます。おすすめは経済専門のテレビや新聞、Webサイトでの情報収集です。経済のニュースに絞って情報収集できるので、効率がよく勉強にぴったりと言えます。
経済専門のメディアもたくさん存在しているので、やさ株編集部が実際に使っていておすすめできる媒体を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
| メディア名 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|
| モーサテ | テレビ番組 | 平日の朝5:45から放送の経済番組。経済の動きをいち早く、わかりやすく解説している。朝の支度をしながら聞き流すところからはじめてみよう。 |
| WBS | テレビ番組 | 平日の夜22:00から(金曜日は23:00から)放送の経済番組。モーサテと同様に経済の動きをチェックできる。その日のニュースを把握できるので、家事をしながら流し見してみよう。 |
| 日本経済新聞 | 新聞・Web・ アプリ |
経済関連の情報収集をする定番ツール。経済や投資、企業に関するニュースをチェックできる。アプリもあるので、移動中などでもかんたんに情報収集が可能。有料契約がおすすめだが、最初は無料会員からスタートしてみよう。 |
| ブルームバーグ | Web | 日本経済新聞と並ぶWebニュースサイトの定番。経済に関するニュースをチェックできる。毎朝投稿される「今朝の5本」をチェックするだけで、世の中の動きを把握できる点が便利。無料で利用できる。 |
関連記事
ステップ⑥ 保有株の業績をチェック
株式投資をスタートしたあとは、四半期ごとに発表される決算を確認して「経営に問題がないか」、「想定どおりに成長しているか」などをチェックしましょう。
この際に使うのが「決算書」です。決算書にはいくつか種類があるのですが、四半期ごとの業績推移では「決算短信」をチェックするのが基本となります。それでは、決算短信とはどのような書類なのかを見てみましょう。
決算短信には、最新決算の業績や経営成績に関するコメントなどがコンパクトにまとまっています。しかし、基本的には文字と数字が並んでいるだけなので、初心者にとっては心理的なハードルが高い書類です。
もちろん、慣れてしまえば決算短信から情報をサクサク入手できるのですが、逆に言うと慣れるまでは情報収集に時間が掛かります。まとまった時間の確保がむずかしいサラリーマン投資家にとっては、大変な作業と言えるでしょう。
このような課題を解決するため、各証券会社が「決算を効率よくチェックできるツール」を提供してくれています。口座開設すれば無料で使えるので、ツールを手に入れて効率的に決算分析したいですね。
今回は、数ある証券会社の決算分析ツールの中から、初心者向けを2つ、脱初心者向けを3つ紹介します。
| 投資家レベル | ツール名 | 証券会社 |
|---|---|---|
| 初心者向け | 銘柄スカウター | マネックス証券 |
| moomooアプリ | moomoo証券 | |
| 脱初心者向け | マーケットラボ | 松井証券 |
| 日本株アプリ | ||
| 財務分析ツール | GMOクリック証券 |
初心者の方は、まずマネックス証券とmoomoo証券に口座開設して、銘柄スカウターとmoomoo証券で取引&ツールを使える状態にしておくのがおすすめです。その後レベルアップしたら、松井証券とGMOクリック証券にも口座開設して、マーケットラボや日本株アプリ、財務分析ツールを使うようにしましょう。
証券会社の口座は1つしか開設できないわけではありません。複数の証券会社に口座開設できるので、ぜひ検討してくださいね。それでは、おすすめ決算分析ツールを見ていきましょう。
初心者向け①マネックス証券「銘柄スカウター」
マネックス証券の「銘柄スカウター」は、私たち投資家の銘柄分析を効率化してくれる最強のツールです。先ほど紹介したように、決算短信は数字と文字が並んでいるだけなので、視覚的にチェックするのがむずかしくなっています。
銘柄スカウターでは、売上高や営業利益率、ROEなど重要な業績指標をグラフでチェック可能です。さらに、2007年から現在に至るまでの業績をグラフ化してくれているので、“過去数年分の決算短信を開いてExcelに数字を入力し、グラフを作成する”といった手間が省けます。
さらに、貸借対照表の図解が載っているので、財務健全性を一目でかんたんにチェックできる点も魅力です。
このほかにも、脱初心者レベル以上の方が重宝する指標がたくさん載っています。自分の成長に合わせて使い込んでいけるツールなので、株式投資をはじめる際に必ず手に入れておきたいツールです。
銘柄スカウターは、マネックス証券に口座開設すれば誰でも無料で使えます。ぜひ有効活用して、効率よく決算分析していきましょう。
初心者向け②moomoo証券「moomooアプリ」
moomoo証券が提供している「moomooアプリ」は、個人投資家の情報収集を効率化してくれるツールです。米国株メインのイメージが強いですが、日本株の情報も充実しています。具体的には、業績推移や財務指標などの分析に必要な指標をグラフで確認可能です。
特に「ビジネスデータ」が便利で、分析対象企業の重要指標をグラフでチェックできます。例えば任天堂(7974)の場合、「Nintendo Switchのハード販売台数」や「ソフト販売本数」がグラフで載っているのです。
売上高や営業利益率の変化を解像度高く分析するには、ハード販売台数やソフト販売本数といった売上高の構成要素に分解してチェックする必要があります。これまでは決算説明資料に載っている数値をExcelに転記して分析しなければなりませんでした。moomooアプリがあれば、この手間が省けてとても便利ですね。
moomooアプリは、ダウンロードすれば誰でも無料で使えます。口座開設すると、moomooアプリ1つで銘柄探しと分析、取引まで完結するためとても便利です。
当サイト経由でmoomoo証券に口座開設すると、「moomooアプリ完全解説レポート」をプレゼントするタイアップキャンペーンを実施しています。株初心者の方にぜひ使っていただきたいmoomooアプリの機能を、スクリーンショット付きで解説するレポートとなっています。
「株初心者の方はこの機能だけ使えばOK」というものに絞って紹介しているので、この機会にぜひゲットしてください。
脱初心者向け①松井証券「マーケットラボ」
ここからは、脱初心者向けのおすすめツールを紹介します。1つ目は、松井証券の「マーケットラボ」です。銘柄分析や株価分析を効率化してくれる強力なツールとなっています。
マーケットラボには、「過去20年分の損益計算書の数値」や「業績の時系列推移(グラフ)」、「過去のPER推移(ヒストリカルPER)」、「大量保有報告書の提出状況」など、分析に必要な機能がたくさん搭載されています。
下の画像は、業績の時系列推移をグラフ化したものです。売上高や営業利益、経常利益、当期純利益(下の画面では最終利益)を見渡せるようになっており、業績の全体像を視覚的にチェックできます。
脱初心者向けの機能も充実しています。「信用残・証金残」や「空売り(からうり)残高」、「大量保有報告書の提出状況」といった株価分析に役立つ情報をチェック可能です。
例として、「信用残・証金残」という機能を見ていきましょう。この機能に含まれている「貸借倍率(たいしゃくばいりつ)」と呼ばれる指標を確認することで、株価が上がりやすいか下がりやすいかを判別できます。今回は詳しい説明を省略しますが、脱初心者以上の方にとっては便利な機能です。
貸借倍率を使いこなすためには、信用取引の考え方を理解しておかなければなりません。「信用取引とは?」で詳しく解説しているので、気になった方はこちらのページをご覧ください。
マーケットラボを使えば、保有銘柄や気になっている銘柄の業績や株価動向を、プロ並みのレベルでスピーディーに分析できます。松井証券に口座開設すれば誰でも無料で使えるので、この機会に口座開設しておきましょう。
口座開設料・年会費などは一切かかりません。
脱初心者向け②松井証券「日本株アプリ」
2つ目は、松井証券が提供している「日本株アプリ」です。財務分析と株価分析の機能が充実しており、アプリ1つで情報収集から取引まで完結します。特に株価分析の機能が充実しており、有料級の機能が無料で使える点で高い人気を誇ります。
中でも人気の機能が「売買分析」です。銘柄ごとに“当日どのような取引があったか”を確認できます。「機関投資家の空売り状況」もチェックできるので、株価が急変動した場合の状況確認に役立つと個人投資家の間で重宝されています。
日本株アプリが登場するまで、機関投資家の空売りをチェックする場合、専門サイトを開いて確認しなければなりませんでした。また、無料のサイトでは機関投資家の空売り状況を“取引終了時点で”集計していました。このため「機関投資家が空売りし当日中に買い戻した」場合、取引終了時点で空売りが解消しており、機関投資家の動きを把握できないという課題があったのです。
日本株アプリでは、この課題が解決されています。取引終了時点ではなく、取引そのものを記録する方法(約定ベース)を採用しているため、機関投資家の空売りを正確に追いかけることが可能です。
少し専門的な機能ですが、有料級のものを松井証券に口座開設するだけで誰でも無料で使えるのは、とても魅力的ですよね。ご自身の投資家レベルがアップした場合に使いたくなる機能なので、今後のためにも松井証券に口座開設&アプリダウンロードをしておきましょう。
口座開設料・年会費などは一切かかりません。
売買分析の使い方については、下の記事で詳しく解説しています。気になった方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
脱初心者向け③GMOクリック証券「財務分析ツール」
3つ目は、GMOクリック証券が提供している「財務分析ツール」です。こちらは、銘柄の財務分析に特化したツールとなります。
財務三表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)をグラフで確認できるほか、より深い分析をおこなうために必要な「経営効率分析」と呼ばれる機能や「理論株価シミュレータ」が搭載されています。特に経営効率分析は、脱初心者を目指す方におすすめの機能です。
経営効率分析では、「ROIC(ロイック・投下資本利益率)」という指標を使って分析します。これは、事業を運営するために投じた資本(投下資本)を使って、どれだけ効率よく利益を生み出しているかを表す指標です。パン屋を例に考えると、パンを焼く機械やお店の建物を効率よく使って儲けているかがわかります。
まずは、ROICが上昇しているかどうか、効率よく経営できている目安となる7%を超えているかをチェックしてみましょう。
経営効率分析では、ROICを構成要素に分解した「ROICツリー(上の画像)」も載っています。営業利益率や投下資本回転率など、ROICを構成要素に分解して詳しく分析可能です。
任天堂の場合、ROICが少し低下しています。これは、ROICの構成要素である「売上高営業利益率」と「投下資本回転率」が低下したためです。さらにこれらの構成要素に目を向けると、「販売管理費率」の上昇と「運転資本回転率」と「固定資産回転率」の低下が背景にあることがわかります。
以上をまとめると、経営効率が少し落ちてきていることがわかります。ここまで調べたら、同社が公表している決算書やニュースを確認して、なぜ経営効率が落ちているのかを調査しましょう。ROICの構成要素にも注目すると深い分析ができるので、慣れてきたら注目したいですね。
このほかにも、GMOクリック証券の財務分析ツールには「理論株価シミュレーター」という最強機能が搭載されています。理論株価とは“会社のあるべき株価”のことで、市場で付けられている株価と比べて割安性を判断できます。
理論株価シミュレーターでは、理論株価の計算で使うパラメーターを自分で設定し、それに基づいて理論株価を計算できる点が特徴です。専門的な知識が必要になるので、投資に慣れてきたら使ってみましょう。
GMOクリック証券の財務分析ツールは、財務分析に必要な基本的な機能から、マニアックな機能まで充実しています。口座開設すれば誰でも無料で使えるので、企業分析をより細かく、プロと同じようなレベルでおこなうためにも、ぜひGMOクリック証券に口座開設してくださいね。
口座開設料・年会費などは一切かかりません。
まとめ
株初心者に向けた株式投資のはじめ方や勉強方法を、6つのステップで解説してきました。ステップ①から順番に取り組めば、誰でも株式投資をスタートできます。
また、当サイトでは株初心者向けの記事をたくさん書いています。株式投資の基礎から応用まで学べる「株初心者入門講座」や投資の悩みを解決できる「株のお悩み相談室」は特におすすめです。
株式投資に勉強は付きものですが、世の中の動きやビジネスに敏感になれるので、仕事にもプラスの影響があります。また、失敗することもあるかもしれませんが、次の投資に生かせばOKです。学んだことや経験したことは無駄にならないので、一緒に株式投資の一歩を踏み出してみましょう!
この記事を見た人は、こちらも読んでいます